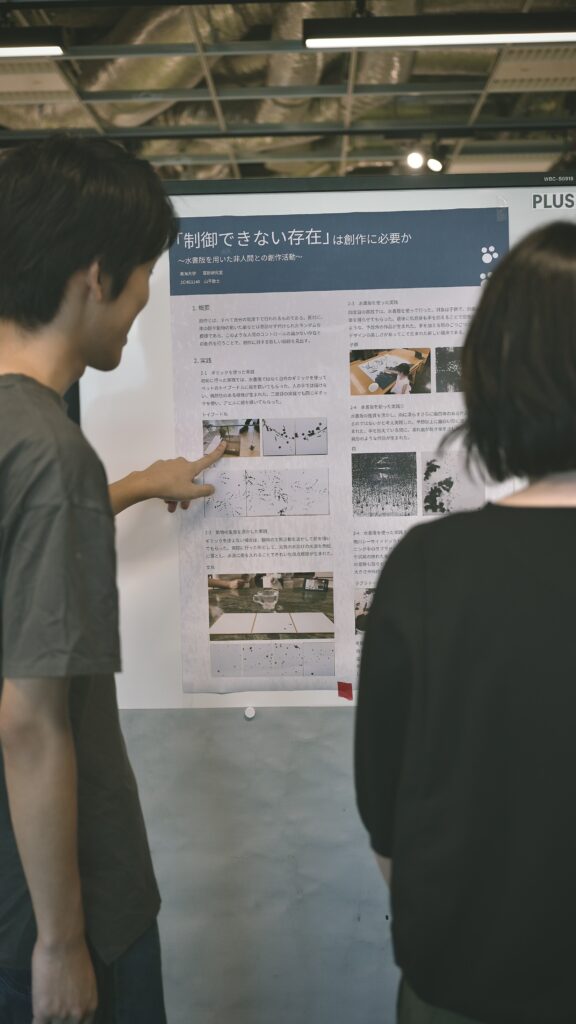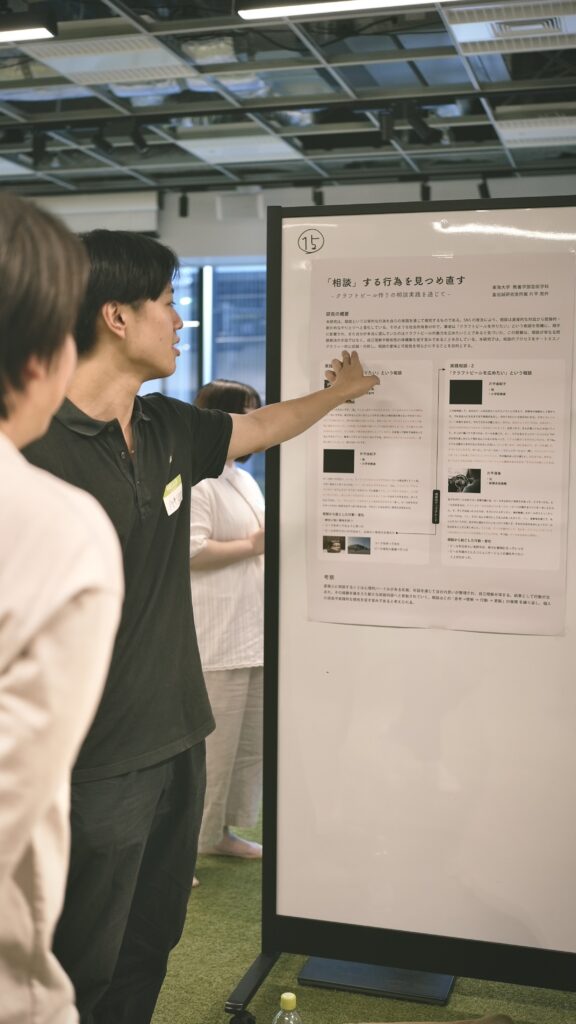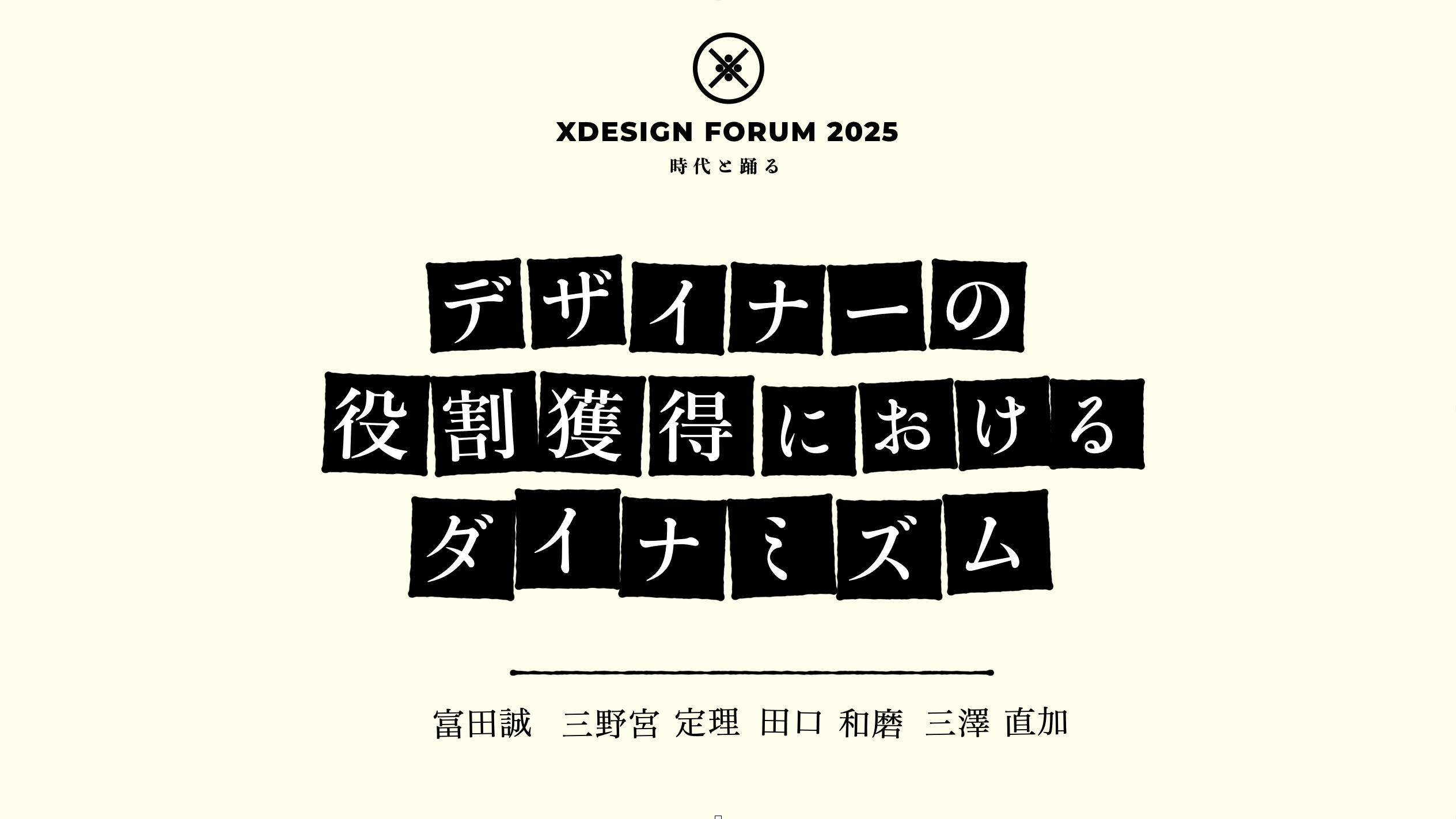好きなアーティストのライブに行った。
曲が始まると、自然と首や手足が自然と動き始めた。
音楽と、環境と、一体となる。
しかし、身体は自分が動かしたと言えるだろうか、
それとも、音楽や他者に動かされたのだろうか。
もしも、時代を音楽に見立てるとすれば、
人は時代に合わせて踊っているのだろうか。
時代に踊らされてしまっているのだろうか。
そして、踊り疲れてしまうこともあるのだろうか。
山崎先生から2025年9月7日(日)のXデザインフォーラム特別セッションの企画検討の依頼をいただいた。AIの発展に伴うデザインキャリアについて触れざるをえないと思った。
平野さんのエントリーはリアリティーがあって衝撃的だ。
「生成AI時代に生き残れるデザイナーを育てるには…」[…]僕はデザイン組織の採用計画を止めた。そして、中央集権的なデザイン組織の解体に向けて動き出し、デザイナーを現場に融かし、埋め込み始めた。現在、30名近く管掌していたデザイナーは、数名になっている。
https://note.com/hiranotomoki/n/na15288ce334a
とはいえ、そもそもデザイナーは常に社会の変化や科学技術の進歩に応じて、その姿を変え続けてきたはずだ。産業革命によって始まった量産品のデザインが、エレクトロニクスの発展に伴う家電デザインが、そして情報機器の登場によるインターフェースや体験デザインが生まれた。デザイナーは常に時代の要求に応じて自らを変えながら、社会の中で粘り強く芸術をしてきたのだ。そう、時代と一緒に踊ってきたのだ。
学んだ「技」が時を経て通用しなくなる瞬間に何度も直面する。この絶え間ない変化にデザイナーはどう向き合えば良いのか。そして、デザイン教育はどうすれば良いのか。そこで、注目したいのが、デザインが立ち上がる瞬間、つまり依頼が始まる前のデザイナーが役割を獲得する瞬間だ。
三野宮 定理:デザイン活動を始めるときに何が起きるのか
デザインとは依頼から始まるように思われがちであるが、実はその前の段階に、デザイナーのアーティストとしての巧みさがあるのではないか。つまり、あるコミュニティーの中で、自分ができること、やりたいこと、求められることの狭間の中で巧みにデザインの仕事を始めていく。この役割を獲得していく瞬間のダイナミズムに焦点を当てて研究したのが三野宮氏である。三宮氏は活動構成型デザインというテーマで博論を書かれた。これらを話題に、活動構成型デザインについて語っていただく予定だ。
富田誠:デザイン活動を立ち上げる経験と学び
次に私は、その活動構成型デザインのコンセプトに呼応し専門外の環境に入り込み創る活動を通じて自分の役割を開拓するという3年生向けのゼミ活動を行なっている。最初に、大学内で学科外の気になる研究室や組織を探し、そこに連絡をとって手伝いという建前で研究室の広報物(紙芝居)を作り、その過程で研究室に居場所を作り、最終的に自分の得意な創作活動を展開するという課題である。これらの課題内容とその成果を紹介したい。
田口和磨:デザイン学生が 就職活動をするとき何が起きるのか
次の話題は、デザインを学んだ学生の就職活動についてである。学生の就職活動は、デザイナーとしての社会的な役割獲得の第一段階と言えるだろう。ここで一体どのようなことが起きているのか、グッドパッチの田口氏にお話をしていただく。田口氏はもともと美術系大学で大学職員として学生募集・学生サービス・進路支援等の業務を経験した後、株式会社グッドパッチに入社され、ReDesigner for Studentのキャリアデザイナーとして、これまで年間100コマ以上の学内ポートフォリオレクチャーや業界研究レクチャーを実施。また年間300名の学生の面談やポートフォリオフィードバック企業とのマッチング支援を行なっている。
三澤直加:サバイブする、 わたしの “野生の 構え”
そして、最後にお話ししていただくのは、共創デザインの会社を経営されている三澤直加氏である。三澤氏は大学でプロダクトデザインを学ばれた後に、UIデザイン、UXデザインの実践、そして起業を経てサービスデザインやビジュアルファシリテーションそしてビジョンデザインなどデザインの活動を常に更新され続けており、執筆から研究など多義に渡る。ここにはどのような「サバイブ」が存在しているのか、そこにある野生の構えについて語っていただく。
このように、取り扱うテーマは広大であるが、デザインの仕事や生き方に迫るテーマにしたいと考えている。ただし、デザインの仕事も、キャリア構築のあり方も状況によって大きく異なるため、時間をかけて文脈を共有しなければ、なかなか共感の得られない話になるかもしれない。少しでも、参加・聴講する方々のキャリア構築の一つのヒントになるような時間にしたいと思っている。
なお、私の担当する特別セッションとは別に
13:00-13:05 オープニング
浅野智(Xデザイン研究所), 山﨑和彦(Xデザイン研究所)
13:05-13:40 キーノートスピーチ「時代と踊る:人類学とデザイン」
伊藤泰信(北陸先端科学技術大学院大学・教授)
15:10-16:30 オープンセッション:口頭発表
16:30-17:40 オープンセッション: ポスター発表
17:50-19:30 交流会
などさまざまなイベントがありますので、
ご関心のある方はぜひ
申し込みはこちらから
https://peatix.com/event/4520759/view
開催後
当日はゼミ学生もポスター発表し、刺激的な学びの時間となりました
佐藤さん:「単純作業から生まれる没頭体験のデザイン」
石田さん:「展示会という場を用いた祖母への理解とアーカイヴ」
片平さん:「相談する行為を見つめ直す — クラフトビール作りの相談実践を通じて」
山平さん:「制御できない存在は制作に必要か」
寺谷さん:「食道癌患者の手術体験支援デザイン」